
蚕業
お蚕飼い
養蚕の流れ
百姓とお蚕様飼いは、かなり古く、田のぼたや野原や家のまわりに飛騨桑や高刈りの桑を植えて飼育してきました。
明治初期には、この地でもすでに相当数の農家が副業として飼育するようになりました。
この頃は、年に二回(春、夏)飼育するだけで、四回も五回も飼育するような技術はまだありませんでした。
その後、だんだんと飼育法の研究が進み、明治三十三年には吉村酒屋に養蚕飼育伝習所が出来、養蚕法を習いに行くようになりました。
明治三十一年には、更に坂下実業学校に養蚕科目が取り入れられ、養蚕熱が高まっていきました。
日清、日露の戦争によって、市場が開け需要が高まっていき出すと益々発展していき、明治四十二年の調査では、五百五十八戸で飼われ、千八百七石も生産されました。
蚕室がどんどん建つ
明治の末期からだんだんと盛んになり、昭和の初期までが全盛期でしたが、第一次世界大戦の頃が一番盛んに飼育され、田には桑を植え野や山を切り開いて桑畑をつくっていきました。この時期に中原、下原は桑園として開墾されました。
殆んどの農家は「百メ取り」を日指して蚕室をどんどん建てていったり、住宅も蚕室兼用に建てるようになりました。今でもところどころ蚕室になった面影が残っています。
このように、どこの村や町でもどこの農家でも盛んに飼育していきましたが、昭和の初期に始まった大不景気により価格は没落していってしまいました。山内誉次郎翁の日記を拾ってみると、昭和六年に一メ目二円五十銭まで下がり、生活が極めて苦しくなっていきました。借金によって建てられた蚕室は、不景気によって返済が出来ず、それでも、百姓は蚕にすがっていくより仕方がなかったのです。
戦いが激しくなってくると、再び盛んになってきましたが、軍需品の生産と食糧増産が強力に押し進められ、全盛期にもたちなおることなく終戦を迎えることになりました。
戦後、化学繊維の発達によりまったく衰退してしまい、昭和四十八年には、新しい形の共同飼育から近代化経営が進められています。
かつて盛大に飼育された頃を思い出して、吉村かなさん(松源地)は、
「お蚕様を年に何回も飼ったぜも。春蚕がすめば夏蚕、次は秋蚕、晩蚕とつづき、それに晩々蚕まで飼ってなも、一息つく間もなかったに。春蚕の時は、桑の木を切って来てその葉を摘んでやぁ飼い、お蚕様のねておらっせる時には田植えの仕度、夜なんぞ疲れてまってねぶとうて起きて飼う時のえらさはまったく口ではいえんぜも。
春蚕は、部屋には炉に山炭を入れて温度をつけならんし、百足(むかで)がよう出て来てくいつくし、子どもが炉へ落ちこまんように気もつけならんし、夏は夏で、夕立のこんうちに桑をつんどかならん、尻かえ、ふやしなどいくらでも仕事があってなも、まったくえらかったぜも。
そうやってせっかくひとねたお蚕様も、病気でくさってしまうことがあり、そんな時は本当にくさりさなも。」
家族がー丸となって働いた様子を目の前に見るように、縁側で夕日を受けながらしわをのばして語られました。
繭(まゆ)の出荷
汗水流して取り上げた繭の出荷は楽しいもので、繭を選別して、袋につめ、馬屋から馬を引き出して鞍をおき町へつけていくのです。
大正の初期、町ではそれぞれの宿屋が臨時繭出荷場になり、仲買人が入り込み、あそこかここか、どこへ売ったら値うちか調べている農家の人、買い取りに忙しい仲買人等、一週間ばかりは町は繭一色になり、活気に満ちた一時を呈しました。
繭代が入って懐(ふところ)が大きくなると、遂い赤い提燈に目が引き寄せられ、一寸一杯ひっかけるつもりが、酔がまわるにつれて、一杯が二杯、二杯が三杯、あげくの果は座敷に上り込み、家族の待っている我が家へ帰った時は、汗水流して働いた金は雀の涙と化していた兵もいたとか。
買い取られた繭は、殆んどは坂下駅から諏訪へ出荷されました。
その後、坂下の製糸屋も大きくなると、それぞれの農家は、自分の好みの製糸屋へ出荷するようになりました。
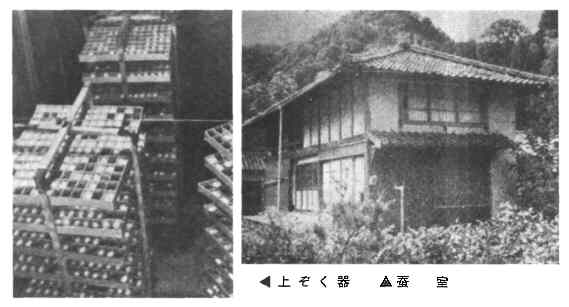
|

